インプラント周囲炎の症状・原因・治療と予防法を徹底解説
2025年09月25日(木)
歯のコラム
こんにちは。岡山市北区津島西坂の歯医者「MAEDA DENTAL CLINIC」です。

インプラント治療を受けた後、「歯ぐきが少し腫れている気がする」「歯磨きのときに出血することがある」といった症状に気づき、不安になった経験はありませんか。それが「インプラント周囲炎」のサインかもしれないと、心配になっている方もいるのではないでしょうか。
インプラント周囲炎は「インプラントの歯周病」とも呼ばれ、初期段階では自覚症状が少ないまま進行します。
放置するとインプラントを支える骨が溶け、最悪の場合インプラントが抜け落ちてしまうこともある怖い病気です。大切なインプラントを長く使い続けるためには、原因や予防法を正しく理解し、早期に対策を講じることが非常に重要です。
この記事では、インプラント周囲炎の初期症状や原因、進行度別の治療法から、今日から始められる予防法、そして気になる費用までを網羅的に解説します。治療後の不安を解消し、適切なケアを実践したい方は、ぜひ参考にしてください。
目次
インプラント周囲炎とは

インプラント周囲炎は、歯科インプラントの周囲に起こる炎症性の疾患で、進行するとインプラントを支える骨が吸収されてしまうことがあります。
歯科医院では、歯周ポケットの深さやレントゲンによる骨の状態などを総合的に確認し、炎症の進行度を判断します。
早期に気付いて適切なケアを受けることが、重症化の予防につながります。
インプラント周囲炎の発症の仕組み
主な原因はプラーク(歯垢)の蓄積で、細菌が歯ぐきに炎症を起こし、放置すると骨にまで影響を与えることがあります。
インプラント周囲の歯ぐきが赤く腫れたり、出血や膿がみられる場合には注意が必要です。
また、レントゲンで骨の変化が確認されることもあり、その場合は炎症が進んでいる可能性が考えられます。
歯周炎との違い
インプラント周囲炎と歯周炎はいずれも歯やその周囲の組織に炎症が起こる点は共通していますが、構造的な違いがあります。
天然歯は「歯根膜」というクッションの役割を持つ組織で骨とつながっていますが、インプラントには歯根膜がなく、直接骨と結合しています。そのため、インプラント周囲炎は炎症が広がりやすく、骨の吸収も進みやすいとされています。
インプラント周囲粘膜炎との関係
インプラント周囲炎は、インプラントの周囲にある骨まで炎症が進行した状態であり、初期段階のインプラント周囲粘膜炎とは異なります。
インプラント周囲粘膜炎は歯肉のみに炎症が限局しており、適切なケアで改善可能ですが放置するとインプラント周囲炎へ進行するリスクがあります。
インプラント周囲炎の症状と診断方法

ここでは、インプラント周囲炎の初期と進行の症状、セルフチェックの目安、さらに歯科医院で行われる診断方法について解説します。
初期症状と進行症状
インプラント周囲炎の初期には、歯ぐきの腫れや出血、違和感といった軽い症状がみられることがあります。進行すると、痛みや膿の排出、インプラントの動揺、口臭の悪化など、より重い症状が現れる場合もあります。
セルフチェックのポイント
ご自身で確認できるサインとしては、歯ぐきの色の変化(赤みや暗い色)、腫れ、出血、ブラッシング時の痛みなどが挙げられます。インプラントのまわりから膿が出る、口臭が強くなるといった変化に気付くこともあります。
ただし、初期のインプラント周囲炎は自覚症状が乏しい場合も少なくありません。見た目に大きな異常がなくても、違和感が続くようであれば注意が必要です。
歯科医院での診断方法
歯科医院では、まず歯周ポケットの深さをプローブと呼ばれる器具で測定し、歯ぐきの炎症の有無を確認します。あわせて、出血や排膿がみられるかどうか、歯ぐきの腫れや赤みの程度も丁寧に観察されます。
さらに、レントゲン撮影によって骨の状態をチェックし、炎症が骨にどの程度広がっているかを確認します。必要に応じてCT撮影など、より精密な検査を行うこともあります。
これらの検査結果を総合的に評価することで、初期か進行した状態かを見極め、適切な治療方針が立てられます。
インプラント周囲炎の原因
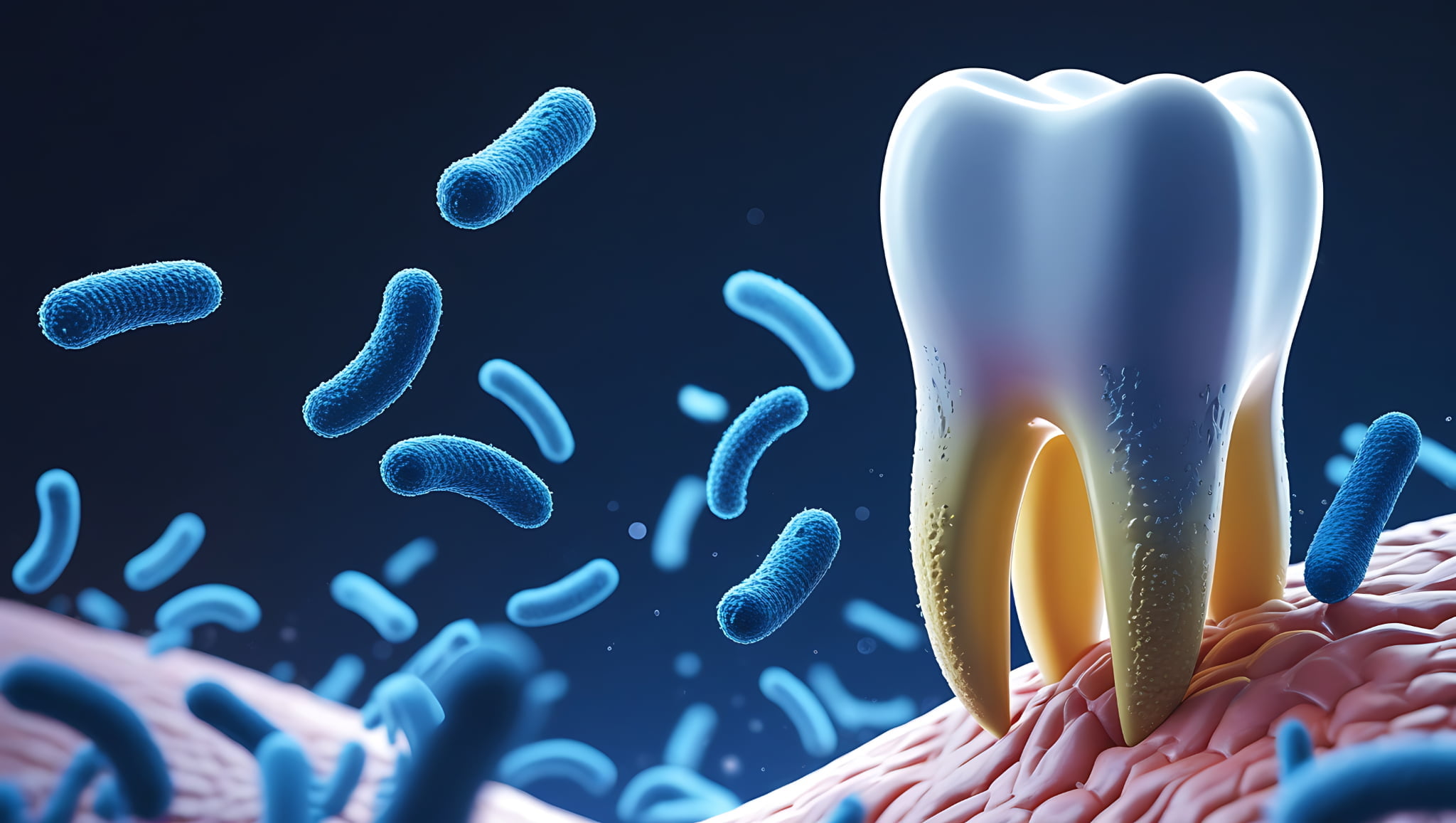
インプラント周囲炎はさまざまな要因で発症します。ここでは、プラークや生活習慣など代表的な原因について整理します。
プラークや細菌感染
インプラント周囲炎の主な原因は、歯とインプラントの周囲に付着するプラークや細菌感染です。プラークは歯磨きが不十分な場合に短期間で形成され、放置すると細菌が増殖し炎症を引き起こします。
特にインプラントは天然歯に比べて歯肉との結合が弱く、細菌が侵入しやすいため、1日2回以上の丁寧なブラッシングや、歯科医院での定期的なメンテナンス(3〜6ヶ月ごと)が推奨されます。
プラークコントロールを怠ると、インプラントの脱落リスクが高まるため注意が必要です。
喫煙や全身疾患の影響
喫煙はインプラント治療後の経過に影響する可能性があるとされ、リスク因子の一つとして指摘されています。
また、糖尿病などの全身疾患も影響を及ぼし、特に血糖コントロールが不良な場合はインプラント周囲の感染や炎症が進行しやすくなります。
これらのリスクを軽減するためには、禁煙や全身疾患の適切な管理が重要であり、インプラント治療前後の健康状態の確認が不可欠です。
インプラントの設計や埋入位置
インプラント周囲炎の発症には、インプラントの設計や埋入位置が大きく影響します。例えば、インプラント体の表面が粗すぎるとプラークが付着しやすくなり、炎症リスクが高まります。
さらに、清掃しにくい位置や角度で埋入されると、日々のケアが難しくなり、周囲炎の発症率が高くなる傾向があります。
インプラント周囲炎の治療法

インプラント周囲炎の治療は進行度に応じて異なります。ここでは、非外科的治療から外科的処置まで一般的な方法を解説します。
非外科的な治療
初期のインプラント周囲炎の場合は、歯科医院での専門的なクリーニングや、抗菌薬の塗布・投与などを行います。これにより炎症の進行を抑え、歯ぐきの状態を改善することが期待されます。
外科的治療
前述した非外科的な治療では改善が見込めない場合は、外科的治療が検討されます。
代表的なフラップ手術では、歯肉を切開してインプラント周囲の骨や歯肉を直接露出させ、炎症組織やプラーク、歯石を徹底的に除去します。手術後は骨再生誘導法(GBR)やエナメルマトリックス蛋白などの再生療法を併用することもあります。
外科的処置が検討されるのは、歯ぐきや骨の状態が進行している場合とされています。
治療期間と通院頻度

治療期間は炎症の程度や口腔内の状況によって大きく異なり、数週間で改善することもあれば、長期にわたる場合もあります。
中等度から重度の場合は、治療が数か月に及ぶこともあり、定期的な通院が必要です。通院頻度の目安としては、初期治療では週1回程度、その後は経過観察やメンテナンスのために月1回程度が一般的です。
治療の進行状況によっては、歯科医師の指示に従い通院間隔を調整することが重要です。
インプラント周囲炎の予防方法

インプラント治療を長持ちさせるためには予防が欠かせません。ここでは、毎日のセルフケアや生活習慣の工夫について紹介します。
正しいブラッシング方法
インプラント周囲炎を予防するためには、歯とインプラントの境目を意識した正しいブラッシングが重要です。歯ブラシは毛先が細いタイプを選び、インプラントの周囲に45度の角度で当てて小刻みに動かします。
1本につき20回程度を目安に磨き、特に歯と歯茎の境目やインプラントの根元部分にプラークが残らないよう注意しましょう。力を入れすぎると歯茎を傷つけるため、軽い力で丁寧に行うことがポイントです。
定期的な歯科メンテナンス
インプラント周囲炎を予防するためには、定期的な歯科メンテナンスが欠かせません。一般的には3〜6か月に1回の頻度で歯科医院を受診し、専門的なクリーニングやインプラント周囲の状態チェックを受けることが推奨されています。
特に、プラークや歯石の除去、歯ぐきの炎症の有無の確認が重要です。また、インプラントの装着状態や噛み合わせの変化も定期的に評価することで、早期に異常を発見しやすくなります。
セルフケアグッズの活用
インプラント周囲炎を予防するためには、セルフケアグッズを活用することも重要です。歯ブラシはもちろんのこと、歯間ブラシ・デンタルフロスなどを活用しましょう。
例えば、歯ブラシは毛先が細く柔らかいものを選び、1日2回以上丁寧に磨くことが推奨されます。
また、歯間ブラシやデンタルフロスはインプラントと歯茎の隙間に溜まりやすいプラークを効果的に除去できます。
さらに、殺菌効果のあるマウスウォッシュを併用することで、細菌の繁殖を抑えることができます。
インプラント周囲炎の費用について

インプラント周囲炎の治療は多くの場合自費診療となります。ここでは、一般的な治療ごとの費用感について整理します。
治療費の目安
インプラント周囲炎の治療費は、治療方法や進行度によって異なります。軽度であればクリーニングや薬の処方で対応できることが多く、比較的費用は抑えられる傾向にあります。
一方で、症状が進行して外科的な処置や骨の再生療法が必要になると、費用は数万円程度から十数万円に及ぶこともあります。
ただし、実際の金額は医院ごとの方針や材料によって異なるため、事前に見積もりを確認するのが安心です。
保険適用の可否
インプラント周囲炎の治療は基本的に自費診療となる場合が多いですが、症状や治療内容によっては一部が保険適用となる可能性もあります。
歯周病治療に準じた処置や、医師が必要と判断した場合には保険が使えるケースもあるため、詳細は歯科医院に確認することが大切です。
まとめ

インプラント周囲炎は、インプラントを支える歯ぐきや骨に炎症が起こる疾患で、早期に対応することが大切です。初期には腫れや出血などの軽い症状が現れ、進行すると動揺や膿の排出といった深刻なトラブルにつながる場合もあります。
原因としては、プラークの蓄積やセルフケア不足、喫煙や糖尿病といった全身の健康状態が関係すると考えられています。治療はクリーニングや薬剤での対応から、外科的な処置まで幅広く行われ、状況に応じて選択されます。
再発を防ぐには、毎日の丁寧な歯磨きやフロスの使用に加え、定期的な歯科メンテナンスが欠かせません。生活習慣の見直しも大切で、禁煙や全身疾患の管理が予防につながります。
費用や保険の適用は治療内容によって異なるため、事前に歯科医院に相談しておくと安心です。
インプラント治療を検討されている方は、岡山市北区津島西坂の歯医者「MAEDA DENTAL CLINIC」にお気軽にご相談ください。
当院は予防中心型歯科診療で歯とお口を守ることを第一にご家族のどの世代にも優しく、より良い歯科医療を提供することを目指しています。